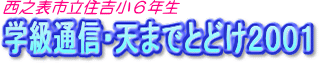
■学級づくり■ ■教育実践資料■ ■サークル案内■ ■Sumi6 ROOM■ ■知己君の「いのち」に学ぶ部屋■ ■PRIVATE■
第71号 みんなが゜迎えた,始業式の朝
第72号 本格的に三学期の生活が始動!
第73号 授業参観・学級PTAが開かれました
第74号 給食週間のポスターを作りました。
第75号 ゴール目指して!(その1)
第76号 国語科「わらぐつの中の神様」の学習より
第77号 フジテレビ・アンビリーバボー「たかしくん,奇跡をありがとう」から学ぶ
第78号 「車いす一日体験学習」に取り組んで~その1~
第79号 「車いす一日体験学習」に取り組んで~その2~
第80号 「車いす一日体験学習」に取り組んで~その3~
| 第71号(886) | |||
| 2002年1月9日(水)発行 | みんなが迎えた,始業式の朝。 | ||
| 昨日は,みんな元気に学校に出てきてくれました。やっぱり,子どもたちがいる学校は,にぎやかで明るいです。 ちょっぴり眠気も残っていましたが,一人ひとりが,やる気を持ち寄ってくれましたよ。とってもいいスタートが切れました。 ※※※ 始業式の朝 OT ー朝ー 目が覚めた。ねむい目をこすりながら起きた。顔を洗って,「寒い」と思った。今日が始業式だと気がついた。朝食を食べた。いつもより,食パンがかたく,食べるのがおそくなった。 ー登校中ー 学校に行くと中でしゅうをぬかして来た。 ー学校に着くと…ー T君と和洋がろう下にいた。暴れていた。T君や秀市君が,「社会のやってきた?」 など,宿題のことを聞くので,冬休みは終わったんだと実感した。 ー始業式ー 始業式は,あくびをたくさんした。でも,児童代表の言葉で目標を聞いて,ぼくもがんばろうと思った。今年(三学期)の目標は,立派に卒業生になることだ。 今日から,三学期 IS 今日から,三学期だ。ねむたいけれど,起きて学校に行った。行くと中で,冬休みも終わってしまったなあと感じた。くつばこに来ると,もうくつが入っていた。休まないでみんな来たんだなと思った。 六年教室に入ると,何かがたりないような気がした。始業式では,私が作文を読むことになっていたので,少しきんちょうしていた。 三学期は,縄跳び大会もあるので,縄跳びの練習をたくさんしようと思う。 始業式の朝 TM 朝起きて思ったことは,「今日から学校だあ。身体測定がある。体重ふえているんだろうなあ」ということだ。私は,始業式もあるんだよなあと思いながら,朝食をとり,学校へ行った。風が強かった。学校について思ったことは,「始業式だ。三学期の目標,決めてないとだ」と頭の中で言っていた。 教室に入ってから目標を決めた。三学期の目標は,「なわとび大会も近いので,二重とびが十五回はとべるようになればいいなあ」ということだ。 始業式も始まったので,目標を達成できるようにこれからがんばりたい。 始業式の朝 YD ほくは,朝起きるとき 「今日から学校か,いややなー。」 と言いながら起きた。でも,学校に行くときは,はりきって走っていった。梶原先生が,信号機の所に立っていて,大きな声で 「おはようございます。」 と言ってくださった。ぼくも, 「おはようございます。」 と返した。その一言で,「今日もがんばるぞ」と心の中で思った。 学校について,みんなに「おはよう。」と言った。久しぶりのみんな,久しぶりの学校だった。そして,始業式が始まった。校長先生が,「三学期の目標はありますか。」と聞かれた。ぼくは,まだ決めていなかった。ぼくは,ちゃんときめないとと心の中で思った。こうして始業式は終わった。 始業式の朝 KY 今日は,いよいよ始業式だ。私は,昨日の夜,作文が残っていたので,夜遅くまで起きていた。なかなか案がうかばないので,少しずつ書いてみると,だんだん案がうかんできた。時計を見ると,夜の二時だ。明日の朝,早く起きて書こうと思い,すいみんに入った。 「ガチャンガチャン」…。 「Y,今日学校やろー。」 お母さんの声。いっしゅん的な朝だ。「あ,学校だ~。」と心の中で思っていた。今までの冬休みで,早起きしたのはほとんどない。だから,そのクセと,ちょっと寒さとねぶそくで,なかなか起きられなかった。自分では起きようと思っているのに起きられない。六時五三分くらいに起きた。制服の買い物もあったので,いそいでご飯を食べ,作文を書いて,着替えてといそがしかった。まだすごくねむたかった。私は,時々「もう今日学校休むー」と思った。 車で学校へ行き,日高店で制服を買い,着て学校へ向かった。…途中,略… さっそく朝の会が終わってから始業式だ。まともにご飯を食べていなかったので,少しきつかった。でも,身体測定があるので,グッドタイミング。始業式は早紀さんが読む。早紀さんはかぜだったから,大丈夫かな。校長先生のお話もあったけれど,すぐに終わりました。 私の目標は何だろう。三学期もがんばろう。早ね,早おき。 始業式の朝 US 「ビュー。」 外の風を耳にして,ぼくは起きた。今日は,始業式だ。早く学校へ行かなきゃと思った。久しぶりの学校なので,みんなに会えるのが楽しみだった。 学校について,久しぶりに会えたので良かった。始業式が始まって,これから三学期だけど,たのしい思い出を作っていきながらいい小学校生活をおくって卒業していきたいです。 始業式の朝 HT 今日は,学校です冬休みも終わりました。ぼくは,なかなか朝起きることができませんでした。 学校についても,あまり学校という実感がありませんでした。友だちや先生が来ると,何となく学校という実感がありました。 ぼくは,あと三ヶ月しかない小学校生活なので,くいのないように楽しくすごしたいと思います。 始業式の朝 HS 今日,朝起きたときに思ったことは,「今日から学校か~。もうちょっとねたい。」ということだった。正直に言うと,「いや」という気持ちの方が多かった。でも,久しぶりにみんなに会えるのか~」と思うと,ちょっと,楽しみになってきた。 冬休みは,起きたとき,九時以降がほとんどだった。夜も,夜更かしが多かったので,学校に行って,生活のリズムをかえたいと思った。 なつかしい教室へ入ると,友だちとおしゃべりをした。久しぶりにこんなに話したなと思うくらいだった。 始業式では,六年生代表として,早紀さんが発表してくれた。とてもいい発表ができて,すごいなと思った。久しぶりに学校のそうじもした。 家にいるとたいくつ時が多いけど,学校は友達といるだけでたいくつしないので,いいなあと思った。 身体測定は,体重がかなり増えていた。おかしを食べ過ぎたからかな~と思った。三学期は,冬休みにちょっと体力を失ったので,取りもどしたい。 あと三ヶ月で卒業だ。ぜんぜんそんな感じがしないけど,いろんな事に積極的にとりくんで,りっぱな六年生として卒業したい。 残りの三ヶ月,がんばるぞ。 ■田上病院訪問から学んだこと・感想文② ◇◆◇HS 今日,田上病院のクリスマス会へ行った。車がむかえに来てくれた。車の中ではじめのあいさつの練習をしたり,いろんなことを考えていた。田上病院に着くと,優しそうなかんごふさんがむかえてくださって,三階へ案内してくださった。三階には,もうたくさんの人たちが集まっていた。準備をして,ステージへ行った。ほとんどの人が車いすに乗っていた。 はじめあいさつをした。きんちょうして,顔が赤くなっているのが分かった。はじめは,「空を飛べるよ」だった。声の大きさはすごくよかったと思う。八人が一つになれたような気がした。泣いている人もいた。次に,「ふるさと」を笛でふいた。何カ所かまちがえてしまったので,「風を切って」でばんかいしようと思った。高いところで,ふけなかったところがあった。昨日,家でたくさん練習したから,ちょっと悲しかった。でも,「アンデスの祭」がけっこううまくできたのでよかった。そして,次に「荒馬」と「ソーラン節」と「南中ソーラン」を続けてした。まずは,荒馬。曲が流れて始まった。大前進で,ステージへ入っていった。三時間目に先生に注意されたことを頭の中に入れておどった。今日は,あまり大きな失敗されたことを頭の中に入れておどった。今日は,あまり大きな失敗をしなかったのでよかった。次は,ソーラン節。長半天を着て,ステージに立った。かけ声も,ちゃんと大きな声で出せたのでよかった。 「はいっ」Yさんの声がひびいた。そしてその後に,私たちも返事をするようにして「はいっ」と言った。一つひとつの動作に気持ちをこめた。「ドッコイショドッコイショ」「ソーランソーラン」など,ちゃんとかけ声も出せたのでよかった。終わったとき,大きなはくしゅが聞こえて,何となくてれくさかった。 ひかえ室へ行ってから,すぐボランティアで,おじいちゃん,おばあちゃんのとなりへ行って,残りの人の発表を見たりした。かんごふさんが, 「あなたは,この人のとなりにいてくれる?」と言って,私をつれていってくれた。かんごふさんは,私が,となりにいるということをそのおばあちゃんに教えていた。何をしていいか分からず,ただとなりにすわっていたら,かんごふさんが, 「このおばあちゃんは,言葉はしゃべれないけど,ちゃんとわかってるんだよ。手をにぎってごらん。」 と言われたので,私はおばあちゃんの手をにぎった。すると,そのおばあちゃんは,自分の手と私の手を見てびっくりしているようだった。そして,すぐ泣いていた。私は,今までえらいことをしたこともないし,すごいこともしていないふつうの女の子だ。こんな私が,手をにぎっただけで,うれしくて泣いてくれるなんて,うそかと思った。 それから,サンタさんが来て,プレゼントを配った(ちゅうせん)。私たちも,配ったりするのを手伝った。プレゼントの番号が書いてあるのを見せてくれなかったりする人もいて,意外と大変だった。車いすのかいごをするのはできなかったけど,たくさんのおじいちゃんとふれあえたのでよかった。また,このような機会があったら,積極的に参加して一人でも多くの人に元気(心も体も)を与えられたらいいなと思う。 今日は,T君が,「荒馬」をおどれなかったので,今度わかさ園に行って,またおどるときは八人でおどりたいなあ~。今日分かったことを,これからに生かしていきたい。 ◇◆◇YD 今日,田上病院のいもんに行きました。まず,初めに歌を歌いました。最初から感動している人もいました。その歌が終わり,次は,リコーダーをしました。何か所かまちがえました。すごくきんちょうしました。次は,ぼくも何回も練習したギターをしました。その歌は,『アンデスの祭り』というのをしました。ぼくは,おもいっきりひきました。少しまちがえたけど,よかったです。最後に荒馬とソーラン節と南中ソーラン節をしました。荒馬はかなりうまくできたと思います。ソーラン節はあまり声が出ませんでした。でも,秀市君ともいきがぴったりあっていたので,よかったです。そして,南中ソーラン節。すごくきんちょうしました。でも,最後はすごくきれいにきめられました。そのあと,大きな拍手をもらったので,うれしいでした。 そのあと,ボランティア活動をしました。クリスマスプレゼントなどをわたしたりしました。おばあちゃんとも話したりしました。 最後に田上病院の見学をしました。すごい機械だらけでした。手術室なども見ました。見て回っていると少しこわくなりました。薬なども見ました。すごい数でした。ぼくは,「薬って,こんなにあるんだなあ。」と思いました。ほんとうにびっくりしました。 教えてくださった方々は,ていねいに教えてくださいました。そして,最後におかしももらって帰りました。帰るときも,「本当にありがとうございました」と言われたので,やってよかったなと思いました。とつてもいい学習になりました。 |
|||
| 戻る | |||
| 第72号(887) | |||
| 2002年1月16日(水)発行 | 本格的に三学期の生活が始動! 目指すは,三月二十二日。 |
||
| 三学期が始まり,二週目に入りました。ちょっと,朝からぼーっとしていることもありますが,何とか子どもたちの生活も平常通りに回転し始めました。これから,みんなで元気を出して盛り上げていきたいと思います。 さて,子どもたちはさっそく卒業アルバム作りにとりかかっています。みんな,パソコンの操作にも慣れて,素敵なアルバムができあがりそうです。 また,国語と算数では,「漢字力・計算力アップ大作戦」として,小学校の漢字と計算のドリルに毎日取り組んでいます。自分のつまずきを発見して,家庭学習でも復習を位置づけてくれたらと思います。 さらに,縄跳び大会に向けての練習も始まっています。只今,体育館の黒板には,現在の最高記録を書き出すようにしていて,みんなで新記録への挑戦を続けています。 このように,たくさんの取り組みが,同時進行で進んでいきますが,学級目標「みんなが,みんなでのびていく」を合い言葉に,卒業式というゴールを目指して,しっかり歩いていきたいと思います。 ※ 明日は,授業参観・学級PTAとなっております。三学期の子どもたちのはりきる様子を見に来ていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。 ■子どもの目~生活日記より 逆上がり IS 今日,逆上がりの練習をしました。 「一,二,三。」 くるっと回って着地。 なんと,逆上がりができたのです。まるで,夢を見ているようでした。 とっても,とってもうれしかったです。 (一月十日) ※ISさんの一つの目標は,逆上がりができるようになるということでした。それを,とうとう達成することができました。やっぱり,あきらめてはいけないんだね。よく頑張った。拍手。 ■田上病院訪問から学んだこと・感想文③ ◇◆◇KY 今日,田上病院へ行った。私たちは,田上病院にどのような施設があるかというのも調べることになっていた。私は,ISさんと一緒に踊りのことを説明することになっていた。三時間目にリハーサルもした。MDが電池切れになって,南中ソーランは踊れなかった。すぐに近づいてくる。昼休みは,十分には何もかもすましておいた。三十分に車が来るということだった。セリフがやばかったので,ISさんと一緒に練習した。高橋先生が,ビデオカメラを準備していた。YD君が,「あと十分で車くるよー。」と言った。黒い車と白い大きな車だった。私たち女子4名は行きは黒い車に乗った。車の中でもセリフの練習をした。一緒に言うところがなかなか合わない。私は,そこのセリフだけ,少しISさんにまかせた。「田上病院!」 「田上病院ついちゃったよー。」 車からおりた。トランクつんできたギターやふめんだいをおろした。男子も到着。しかし,運転手さんは,そのまま行ってしまいました。準備ができました。いよいよ中へ行きました。エレベーターは中が広く,ふつうのエレベーターよりゆっくりでした。ボタンの位置も中にあったり,外からでも障害者の方々もできるように設定してありました。そして,早くもまた来ました。ついたら,にもつをまとめたりしました。たびもはいて,準備ばんたんになったら,「クリスマス会場」とかいてあった部屋へ行きました。 まず,はじめの言葉を言ってから,YD君が歌のことについて言った後に,「空を飛べるよ」を歌いました。声がちょっとやばいでした。拍手をもらいました。次に,「ふるさと」「風を切って」「アンデスの祭」を笛で合奏しました。できるだけ見ないようにしたけれど,不安で,というようなくり返しでした。そして,私が,不安なセリフです。最初の言葉は成功したけれど,一緒に言うところを忘れてしまい,「がんばります」と言えと言われたので,「がんばります」と言いました。とても恥ずかしいでした。 そして,荒馬が始まりました。荒馬がななめになったり,踊りが小さくなってしまったりしました。でも,覚えていたのでよかったです。次に,ソーラン節。「そーれひけヨイショ」というところが,最初声が裏返ってしまって,はずかしいでした。でも,大きな声で言うことができて,よかったです。踊りの最後の「南中ソーラン節」。荒馬・ソーラン節が前にあったので,少し苦しいでした。でも私は,患者さん,自分たちにも喜びがくるので,苦しくても,一生けん命がんばっておどりました。そして,最後に終わりの言葉。大きな拍手をもらうことができました。私は,このおじいちゃんおばあちゃんたちが,患者でも笑顔で見守っていてくれたのでうれしいでした。 次は,ボランティアです。うでにつけておじいちゃん,おばあちゃんたちのそばについていてあげていました。私は,お年寄りになると車いすなどになるんだなあと思いました。あとから,大人や小さい小学生が踊っていました。おじいちゃん,おばあちゃんたちにくじをひいて,サンタからその番号のプレゼントをもらっていました。私は,このようなことでも子どもとおじいちゃんやおばあちゃんとのふれあいができるのかなあと思いました。 その後,見学に行きました。「1日に来る患者さんは500人~700人ぐらい。」と言われ,びっくりしました。すぐにけんさ(手術)できるように救急車から運ばれたら,救急処置室に運ばれ,変だったらとなりのベッドに移す。かげができないライトなどがあり,けんさなどができるようになっていました。手術室には,ばいきんが入らないように,せいけつに,くつはぬがなければならないらしいです。脳・体半分がけんさできる部屋もありました。それは,1億ぐらいはするらしいです。 私は,この田上病院にきて,患者さん達のあたたかさ,田上病院のことについて知ることができました。もっともっと調べてみたいです。それに,患者さんだけでなく,自分たちにもよろこびができました。これも思い出の一つです。とても楽しいでした。(楽しかったせいか,すごくはやく感じた。) 説明をしてくださった看護婦(士)さん,HT君のお母さん,田上病院のみなさん,今日は,ありがとうございました。 |
|||
| 戻る | |||
| 第73号(888) | |||
| 2002年1月18日(金)発行 | 授業参観・学級PTAが開かれました | ||
| 昨日は,授業参観・学級PTAが開かれました。忙しい中,ご参加下さったみなさん,ありがとうございました。また,いろいろな都合で出席できなかったみなさん,子どもたちはがんばってくれましたのでご安心下さい。 授業参観は,「とびうお」での「いのちの学習」を行いました。子どもたちの調べ学習への指導の詰めが甘く,途中でひっかかってしまい,計画したところまで行きつきませんでした。自分自身の「いのち」を過去から「生命」の連続として捉えるということと,自分以外には存在しない固有のものであるということを捉えさせたかったのですが,またこの次の時間に補っていきたいと思います。 学級PTAでは,三学期の学級づくりと卒業関係の取り組みについて話をさせていただきました。とにかく,子どもたちが胸を張って中学校へと進んでいけるようにがんばりたいと思いますので,ご協力をよろしくお願いいたします。 卒業関係では… ・アルバム制作に,二~三千円かかりそう ・卒業文集は,保護者の原稿も載せる ・卒業記念品は,学校の希望を聞く ・卒業記念親子製作としてガードレールのペインティングを行う方向で進める といったようなことが話し合われました。 最後には,お一人ずつ冬休みの生活を振り返っていただきました。どの子も,お手伝いをよくし,年末年始を楽しく過ごせたようでした。 いのちの授業の感想~その一 ■YD ぼくは,いのちの学習をしてちょっとむずかしいなあと思いました。でも,ぼくたちのたん生は,二つあることを知りました。一つは,生命のたん生で,ぼくたちのずっと前の先祖が生まれた時が一つある。二つ目は,自分たちがお母さんのおなかの中から生まれてきた時です。 あと,最初生まれた生き物は,動物だと思っていたが,植物の方から先に生まれてきたんだなあと分かりました。それと,先生から地球のことについて聞かれたけど,ぜんぜん答えられなかったので,しっかりまとめればよかったなあと思いました。これからも,たくさん調べたいです。 ■IS 今日の授業参観は,とびうおの授業だった。私たちが調べたテーマごとに,質問されたりした。私は,答えることができなかったものもあったけれど,できるだけ答えようとした。 いのちのスタートは,生命の誕生から始まったのかなと思った。しかし,自分のいのちの始まりも,いのちのスタートだ! 今日のとびうおは,少しきんちょうしたけど,分かったことがあってよかったなと思う。 子どもの目~生活日記より 早く帰ってきてね!おばあちゃん HS 今日,おばあちゃんが四時半の飛行機で大阪へ行った。小さいころから,おばあちゃんの家に行ってよく遊んだり,歌をうたったり,一緒に買い物をしたりした。毎年,一緒におもちも作った。 私は,おばあちゃんが大好きだから,一年間もずっと会えないのがとってもさみしい。でも,このままだと,おばあちゃんのひざは悪くなるだけだったので,仕方ないと思った。 おばあちゃんは, 「見送りに来たらだめだよ。 したら,ばあちゃん,行くのがイヤになるから。ばあちゃんが元気になってからこいなあ。」 と言っていたけど,私は見送りに行った。 おばあちゃんは,外へ出てから,こっちを見なかった。つきそいのおじちゃんが,「泣いてる」というのを手ぶりで教えてくれた。ずーっと行ってから,おばあちゃんがふり返った。 私は,みんなが飛行機に乗ってから外へ出た。飛行機が飛んでいくのを見たとき, 「もう,会えないんだー。」 と,とても悲しくなってきた。 家に帰るとちゅう,おばあちゃんの家にもよった。おじいちゃんも入院しているので,しーんとしていた。どこからか, 「S,はよー,あがってこいや。」 と聞こえてくるような気がした。 一年も会えないのは,すっごくさみしい。でも,来年いつになるか分からないけど,おばあちゃんが元気な姿で帰ってきてくれれば一番うれしい。 (一月十三日) ※おばあちゃん,きっとはやくよくなって帰ってこられるでしょう。今味わっているその気持ちを,大事にしてくださいね。 今日,畑… KY 今日,お父さんと一緒に上の畑に手伝いに行った。私は,タイヤショベルに乗らなければならなかった(喜)。 まず,畑の中の草を,外に出した。それから,それをタイヤショベルにのせ,下へ落とした。でも,使えないときもあった。お父さんがたいひをまいていたからだ。 タイヤショベルは,とても運転がかんたん。私でさえ,すぐ乗れた。 畑に行くとちゅうで,鹿がいた。こっちを見ながらどこかへ消えた。つのがはえていたので,つっこんできたらどうしようと不安になった。 それから,もう一つの畑まで乗っていった。タイヤショベルは,とてもかんたんでおもしろい。わたしは,これからもどんどん乗りたいです。(一月十三日) ※がんばって手伝いをしてい ますね。とてもたくましいです。楽しく手伝いができることが,素晴らしいと思います。 |
|||
| 戻る | |||
| 第74号(889) | |||
| 2002年1月21日(月)発行 | 給食週間のポスターを作りました。 | ||
| 給食週間の取り組みとして,ポスター作成を行いました。今回は,男女四人ずつに分かれてパソコンで作りました。 まず,何枚かのポスターを分析し,文字と画像の配置や「コピー」について学び,アイデアを出し合いました。大体のデザインが決まったら,給食時間にデジカメを持って取材。その後,パソコンに向かいました。 ここに載せた作品が,子どもたちが作ってくれたポスターです(左・女の子グループ/右・男の子グループ)。 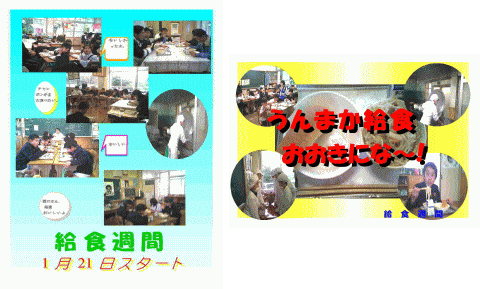 |
|||
| 戻る | |||
| 第75号(890) | |||
| 2002年1月24日(木)発行 | ゴール目指して!(その1) 卒業アルバム・卒業文集作成計画ができました |
||
| いよいよ,卒業に向けての取り組みが本格的に始まりました。やり遂げるべき課題はたくさんあるのですが,その中でも卒業アルバムと卒業文集とは,小学生時代最後の共同制作(目に見える形での)として取り組んでいかなければなりません。 そこで,ようやく一昨日,具体的な作業のスケジュールを話し合い,立ててみました。アルバム作りなど,どうしても昼休みなどの自主的な取り組みがないとできあがりません。正直に言うと,これまでなかなか火がつかず,ちょっとのんびりしていた子どもたちでした。しかしながら,残された日数を確認して冷や汗タラリ…(担任も,タラリタラリ…)。 さっそく昨日から取り組みが本格的にスタートしました。その様子は,これから時々「天まで」でご紹介していきます。 ■いのちの授業の感想~その2 □US 今日は,授業さんかんでとびうおの授業をした。先生が,各グループに質問をしました。 「何年前に人類は誕生したか?」 「七百万年前です。」 しずかさんがこたえた。何だかホッとした。 そのあと,先生が,「二つのスタートがある」と言った。その二つのスタートを聞いて,ディーエヌエー(いでんし)のことが出た。話を聞いていると,むずかしくてよく分からなかった。でも,人類の誕生はすごいなあと思った。 □OT 今日のとびうおは,今まで調べたのをふり返って,そこから「私たちのスタート地点」を探そうというのだった。まず,ぼくは,「宇宙の誕生」を調べたので質問をされた。ちゃんと答えられたけれど,先生の話による「宇宙誕生」はもっとくわしかったので,宇宙を調べるのも大変だと思った。 先生が言った,「私たちのいのちのスタート地点」まで,地球上の生命はいろんな進化をとげてきていた。ぼくは,その進化のおかげで今生きているんだと分かった。 □TM 今日の授業参観のとびうおは,いのちの学習でした。宇宙は,「ビッグバン」によってできたということを覚えていた…はずなのに,きんちょうしていたせいか言えませんでした。 その後,みんながまとめたものを少し説明してから,いのちのスタート地点へついた。 いのちのスタート地点は,二つある。一つ目は,「人類の誕生」。二つ目は「私の誕生」でした。 私は,この学習で「わたしのいちは,」何万年も何億年も昔とつながっているんだなと思いました。 □KY 今日は,「宇宙誕生」→「地球誕生」→「生命誕生」→「人類誕生」のことについて調べていたのを発表しました。私は,あせっていて書くだけでした。四グループだったのですぐに番が来ました。先生から聞かれたところは分かりませんでした。私が言おうと思ったことは,全て早紀さんが言いました。だから,なんだか言いづらいでした。先生が, 「植物と動物は,どちらが先に生まれたと思いますか?」と言ったので,私は,本の順番を思い出して,動物かなあと思いました。でも,あとから思うと,きょうりゅうはえさを食べたり,酸素がないと生きていけないので,植物から誕生したと分かりました。 そして,人類の誕生へ行きました。魚類→両生類→鳥類→サル→ほ乳類などで進化していく。そして,二つのいのちのスタート地点があると思う,と先生が言ったので私は一生懸命考えました。 一つめは,生命の誕生の時で,二つめは,自分が生まれたときというのが分かりました。今日は,難しかった勉強で,きん張したけれど,とても楽しいでした。 □HS 今日は,とびうおのまとめをした。「宇宙誕生」と「地球誕生」「生命誕生」「人類誕生」に分けて,まとめていたのを簡単に先生が説明していった。 みていきながら分かったことは,生命が誕生してから,人類が誕生するまで,人類が 誕生するまでかなり間が空いているということだった。その間に,たくさんの生き物が誕生していた。 「いでんし(DNA)」についても話をした。ちょっと難しくて,意味の分からないところもあった。先生が, 「君たちの命のスタートはどこだと思う?」 と聞かれたとき,私は何となく,生命の誕生のところじゃないかな~と思っていたけど,先生が, 「先生は,命のスタートは,二つだと思うな。」 と言っていたので,よく考えると,もう一つはお父さんやお母さん達が生んでくれた時のスタートだった。 授業参観だったので,いつもよりきんちょうしたけど,宇宙,地球,生命,人類が,どのようにして誕生したかなど,いろんなことが分かったので,よかった。自分のグループのたりないところをもっとしないといけないと思った。 □HT 今日,命の学習をした。今日は,授業参観だった。まずは,今まで調べてきたことを復習した。ぼくは,地球誕生の係だった。先生に地球がどうやって誕生したのかと言われた時に,答えられなかったので,しっかりとまとめたいと思った。 ぼくは,宇宙が誕生していなかったら,今ここにぼくはいないんだなあと思った。それと,昔から今にまであるDNAは,すごいなあと思った。だけど,ぼくのいでんしを持っているのは,自分だけなので,がんばって生きたいと思う。 |
|||
| 戻る | |||
| 第76号(891) | |||
| 2002年2月5日(火)発行 | 国語科「わらぐつの中の神様」の学習より マサエのおじいさん(大工さん)のように,人の悪いところではなく いいところを見つけられて,それを伝えられる素晴らしい人になりたい |
||
| 久しぶりの発行となりました。「天までとどけ」,書きたいこと・書かなければいけないことが,たーくさんたまっているのですが,いろんなことでばたばたしています。落ち着いて取り組んでいかなければいけませんね。 さて,今日は,国語学習で取り組んだ「わらぐつの中の神様」のおわりの感想をご紹介することにします。複式による指導計画のため,本来なら五年生の教材ですが,今年学習しました。みんな,深く考え,感想もしっかりと書けるようになったと思います。 ■□HT ぼくは,「わらぐつの中の神様」を学習して,おみつさんはすごいなあと思いました。それは,外見でなく中身。気立てがやさしい,くるくるとはたらくなど心がやさしい人なんだなあと思ったからです。ぼくは,かっこよくもなく,くるくるとよくはたらくというわけじゃないけれど,自分はだめだとすぐあきらめずに,自分から変わりたいと思いました。 ぼくは,マサエのおじいさん(大工さん)のように,人の悪いところではなくいいところを見つけられて,それを伝えられる素晴らしい人になりたいと思いました。それに,物の美の価値,用の価値を区別できて,人にも自分自身にも認められる人に自分からなっていきたい。 ■□IS 「わらぐつの中の神様」を学習して,おみつさんのことがよく分かった。おみつさんは,外見はあまりよくないけど,なかみがすごくいい人だ。おみつさんが作ったわらぐつも,外見は不細工だけれど,じょうぶでいいわらぐつだから,おみつさんとにていることが分かった。 物の価値には,美しい価値と使いやすい価値がある。私は,美しい価値の方を見るけれど,使いやすい価値も見ないといけないなと思う。 杉みき子さんは,読者を楽しませる工夫をしていていいなと思った。杉みき子さんの他の作品も読んでみたい。 ■□HS 私は,最初「わらぐつの中の神様」を読んだとき,「どうなんだろう」「これは,こうじゃないかな」と考えながら読んでいた。けれど,何度も読んだり,みんなといっしょに学習しているうちに,新しいことに気づいたりしてきた。それは,一の場面と三の場面のマサエが変わっているということだ。最初は,こたつから出ようとしなかったけど,一番最後には,玄関へ飛び出していったと書いてあったので,話を聞いたことでマサエは変わっている。 他にも,先生に用の価値と美の価値というのを教えてもらった。身の回りのもので考えてみると,付加価値がたくさんあった。 「わらぐつの中の神様」について,ちゃんと学習できてよかった。 ■□US ぼくたちは,あれからくわしく「わらぐつの中の神様」を勉強しました。 それで,マサエは一の場面から三の場面で,どう変わったかなども学習しました。 マサエは,一の場面ではわらぐつの中に神様なんてと言いながら聞いていたけど,三の場面では,雪げたの中にも神様がいるかもと言い,せっきょくてきな姿勢に変わっていた。 他にも,美の価値や使う価値の勉強もした。わらぐつは,美の価値はないけど,雪がふる日は使う価値がある。 雪げたは,美の価値はあるけど,雪がふっているときには使う価値はないと勉強しました。この,わらぐつの中の神様は物の価値を教えてくれたような物語だったなあと思いました。 ■□OT ぼくは,わらぐつと雪げたを類比するときに,全然分からなかった。でも,それは物には必ず価値があるということで,わらぐつには用の価値,雪げたには美の価値があった。そして,全ての物が,その価値を生かした作り方をされているんだと思った。例えば,わらぐつのように用いるために,じょうぶにはきやすいように作っているということだ。 ぼくは,最初の感想で,「マサエはこの話を聞いて,わらぐつに対する見方が変わったんじゃないか」と書いたが,これはわらぐつに対する見方でなく,神様やおじいさんに対する見方が変わったのだった。マサエは,きっと神様のことをえらい,天国とかに出てくるというイメージを持っていたのだと思う。だから,最初,迷信だと言ったんだと思う。そして,「使う人の身になって心を込めて作った物には,神様が入っているのと同じことだ」と言った大工さんがおじいちゃんだと分かり,おじいちゃんに対する見方が変わったんだと思う。 ■□TM 私は,「わらぐつの中の神様」を学習してマサエは一の場面と三の場面では,すっかり変わったなあと思います。一の場面のマサエは,わらぐつの中に神様がいないと言っていて,三の場面では「雪げたの中にも神様がいるかもしれないね」と言っていて変わったなあと思います。でも,おばあさんは「神様」をちがう意味で言っていました。それは,若い大工さんが「使う人の身になって心を込めて作ったものには,神様が入っているのと同じこんだ。それを作った人も神様と同じだ」と言って,マサエはなっとくしていて,最初とは本当に変わったなあと思いました。 それと,おみつさんはすごいと思いました。初めの感想で書いたとおり,自分でお金をためて雪げたを買おうとしてすごいと思いました。 おみつさんの作ったわらぐつは,不細工だったけど,用の価値としてはすごくいい物だったからから若い大工さんも買ってくれて,他のお客さんは見た目で判断して買わなかったんじゃないかなあと思いました。 私は,見た目で判断する物と用の価値で判断する物を区別したいです。 ■□YD ぼくは,わらぐつの中の神様を今まで学習してきて,初めのマサエと三の場面のマサエはちがうということが分かった。はじめ,おばあちゃんが, 「わらぐつをはいていきなさい。」 と言ったけれど,マサエは, 「わらぐつなんかみっともない。」 と言って,わらぐつをいやがっていた。けれど,二の場面でおばあちゃんがわらぐつの中の神様の話をすると,三の場面では,わらぐつの中に神様がいるということを信じて,すごく変わったなあと思った。それと二の場面で,雪げたがほしくて家に帰ってわらぐつを作って,それを市場で売って,お客さんがひどいことを言って,かわいそうだなあと思った。でも,大工さんが 「見かけできまるもんじゃない。使う人の身になって,使いやすく,じょうぶで長持ちするように作るのが,本当のいい仕事だ。」 と言って,すごくいいことを言うなあと思った。ぼくも,物を買うときは,見た目だけではんだんするので,考えて買いたいです。ぼくは,この勉強を通じてこんなことが分かりました。 ■□KY この「わらぐつの中の神様」を学習して,作者も読者のことを考えていることが分かりました。題名をつけるのにも努力をするんだなあと思いました。初読だったら,びっくりするところがあったりするけれど,再読だったらおみつさんは誰かなど分かります。 そしておみつさんは,美しいものへのあこがれで,雪げたがほしかった。しかし,家の状況・自分の立場があるから,買うのがむずかしい。おみつさんは,自分でわらぐつをあんだ。わらぐつは,よごれてもいいようにはでにしなくてもいいし,付加価値もあまりない。それにくらべて,雪げたは特別な何かがあるときなどにはいていく。人や物は,外見ではなくその本質が大事。マサエは,一の場面では,「そんなの迷信でしょ。」と言ったり,あまりわらぐつをはきたがらなかった。でも,おばあちゃんの話を聞いた後,三の場面では,すぐふみだいを持ってきたり,おじいちゃんがお風呂から帰ってくると,赤いつま皮の雪げたをかかえたままげんかんへ飛び出して行きました。マサエは,一の場面と比べると変わったことが分かった。 それから,物の本質が大切ということを大工さんは分かっているが,おみつさんや他のお客さんは分かっていなかった。 雪げたは,美の価値。わらぐつは,はく価値。だから,わらぐつは付加価値が無くてもいい。 私は,これからお母さんにねだるばかりでなく,自分でもためてお母さんにOKをもらってから買うようにしたい。 杉みき子さんは,いい工夫をしていて,このわらぐつの中の神様は,とてもおもしろいでした。そして,お金の大切さなども分かりました。 |
|||
| 戻る | |||
| 第77号(892) | |||
| 2002年2月7日(木)発行 | フジテレビ・アンビリーバボー「たかしくん,奇跡をありがとう」から学ぶ 友だちってすごいな,いいなと思った |
||
| 「友だち」について,少し考えてみる必要がある…最近の子どもたちの様子を見ていて,感じていたことでした。思春期の入り口に立つ子どもたちの人間模様なんですね…。 人は,決して一人では生きていけないくせに,「人が人と生きていくこと」はなかなか難しいこと。それは,大人の社会だけではありません。 そこで,子どもたちが「友だち」について少し立ち止まって考えるきっかけを作りたいと思い,先週の道徳の時間にあるテレビ番組を録画したビデオを見てもらうことにしました。 昨年度の六年生も,深く胸を打たれた岡田たかし君の「いのち」が記録されたビデオです(終わりの資料をご参照下さい)。 子どもたちは,真剣に見てくれました。そして,大事なことを学んでくれたと思います。 それでは,子どもたちの感想を紹介します。 ※※※ ビデオの感想 IS 岡田たかし君,十二才。私達よりもひとつ年上の明るい男の子だ。たかし君は,奇せきをおこす人だ。脳こうそくという病気にかかったとき,脳がまひしてしゃべれなかったときに,友達からのはげましの言葉が入ったテープを聞いていた。すると,しゃべれるようになったそうだ。 私は,友達ってすごいなと思った。たかし君は,その後退院したのだが,右にはまひが残っている。 だけど,クラスメイトがくつをとってあげたり,かばんを持ってあげたりと,親切にしていたので不自由ではなかった。そして,たかし君は「何かみんなにしてあげたい」と思うようになった。なんだか,してもらいっぱなしだと,お返しをしたくなるような気持ちは,私にもわかる気がする。だけど,「生きている」だけで,お返しになっているだなと,たかし君は気づいた。 私は,友達が落ち込んでいるときや,病気にかかっている友達がいたら,はげましてあげたいと思う。 ビデオの感想 HT 今日,ビデオを見た。そのビデオは,たかし君の奇跡のビデオだった。ぼくは,このビデオを見て,たかし君やその友だちは,心に思っていることを行動にうつせてすごいと思った。ぼくだったら思うだけ人ごとのように忘れていると思う。それと自分のことだけを考えずに,人の身になって,考えられる人になりたいと思った。ぼくは友達を大切にしたいとも思うけど,友達だけでなく,食物,小さな生き物などの自然に生きている命にも大切にできるようにしたい。 ビデオ見て HS 今日,朝,村末先生がビデオを見せてくれた。そのビデオには,たかし君という男の子が出てきた。たかし君は小さいころ,脳こうそくでたおれて,右半身がマヒして言葉もしゃべれなくなったのに,クラスの友達のメッセージを聞いてしゃべれるようになった。とても奇跡的だなあと思った。 私が今でも心に残っているのは,たかしくんの笑顔だ。友だちと一緒にいる時の顔は,とてもいきいきしていた。 私も,友達といるときは,とっても楽しいし,家族に言えないことだって言えるときもある。 でも,最近,友達関係であまりうまくいっていないことがある。たまに無視されたりしたら,私は,すぐに「何なのあの態度。むかつくなー。」と思うだけで,「何で無視されるんだろう。」「原因が,私にあるのかなー」と深く考えることがなかった。 でも,これからは,相手の気持ちをもっと考えてたかしくんの考えと同じように,友達を今まで以上に大切にしたい。 たかしくんは,友達にも動物に対しても,すごく優しいなと思った。私だったら,うさぎにえさがないと,他の学校の人が行っていても,人ごとみたいに思うかもしれない。なのに,たかしくんは,自分からにんじんを送るなんて,本当に心から優しいんだと思った。 このビデオを見て,本当の優しさと相手の立場にたって考えることの大切さを学べたのでよかった。 たかしくんのビデオを見て US 今日,たかしくんのビデオを見て,感動しました。 たかしくんは,病気にかかりながらも,がんばって生きようとしました。 げきをしたり,うさぎににんじんをきふしたり,とてもやさしいんだなあと思いました。たかしくんは,とても人の役にたったと思います。 ビデオを見て TM 今日,一時間目にビデオを見た。ビデオを見ながら,考えることは,「友達」についてだ。たかし君は,友達に色々してもらっていて,「ぼくになにかできないかなあ」と考えていて,すごいと思った。私だったら,多分考えないと思う。たかし君は,最後に「生きているだけでみんなの役に立つんだ」と,自分で分かってすごいと思う。何でそんな考えを持ったたかし君が,亡くなったのかなあと思った。たかし君は,すごくがんばったんだなあと思う。 感想 YD 今日,一時間目にビデオを見ました。「友達」ということで見ました。 子どもが,脳こうそくをおこしてたおれて,学校からみんなの声が入ったテープを聴いていると,急にしゃべり出して,ぼくは,「友達の力ってすごいんだなあ」と思いました。その脳こうそくのたかし君は,みんなにおかえしをしようと,人形劇をすることにしました。なれない左手で,夜おそくまで,たくさん練習して,これもすごいなあと思いました。でも,。たかし君は,生きているだけで人の役に立っていると言っていました。ぼくは,人の役に立っているのかなあと思いました。 たかし君は,それから一年後に命を落としてしまいました。でも,たかし君は,ぼくたちにいろいろなことを教えてくれたと思います。ぼくは,人を無視したり,ちょっといじめをしたりしたこともあったけれど,相手の立場で考えてみるといやなんだから,これからはあまりそういうことをしないようにしていきたいです。それと,ぼくは今,人にたくさんのことをしてもらっているので,もっと人の役に立てるように,これからも努力をしていきたいです。 感想 KY 今日,「友だち」というテーマでビデオを見た。私は,なんでだろうと思った。とちゅうで,これなんか見たことがあるような気がした。 たかし君は,病気にかかって,友だちの声で,きせきを起こせたりするんだと思った。友だちって,すごいと思った。 学校では,まず教室へ行くと,何も言わないで取り組む学級委員長。友だちだから,すぐにできるんだろうなと思った。私も,悩みがあるときは,友だちに相談できる。一年生と遊ぶ会の時に,一緒に遊べない気持ちは,なんとなく分かる。私もやりたい体育の時,かぜで欠席だった。その時は,一緒にやりたかった。 たかし君は,「みんなにしてもらっているばかりだから,僕も何かみんなのためにやりたい」という気持ちは,すごいなあと思った。でも,最後には,「僕が生きているだけで役に立っている」と言っていた。私は,「そうか,そうなんだ」と思った。 うさぎとふれあうこともできてよかったなあと思った。でも,とつぜん胸が苦しいと言い出した。たかし君は,最後の最後まで生きのびようとしていて,本当に生きたいんだなあということが分かった。 たかし君は,あやさんにも会えて,ウサギともふれあえて,思い出を他にもたくさん作っていて,良かったなあと思った。せっかく生きる希望をつかんだたかし君なのに,とつぜん死んでしまったなんて,かわいそうだと思った。たかし君には,三人のあこがれの女の子達がいて,その三人の女の子もおつやにきた。手紙,べっこうあめ,花束を持ってきてくれていた。もしも,仲が悪かったら,もしかしたら来ないと思うけど,仲がよくて友だちだから,おつやにも来たんだと思う。私は,このビデオを見て,友だちってすごいな,いいなと思った。 ビデオの感想 OT 今日,ビデオを見て思ったことは,このクラスの人たちは,たかし君を支えてあげているし,たかし君も支えてくれている友だちのために役に立ちたいと思っていてえらいということだ。それと,たかし君は,本当に友達が好きなんだと分かった。なぜなら,友だちと一緒に遊べないたかし君が,とてもさみしそうだったからだ。 たかし君は,自分は生きているだけで,他の人の役に立っているんだと言っていた。 たかし君は,他の学校のウサギをすくったり,ダウンしょうとせんこくされてもけんめいに生きている人にさらに勇気をあたえた。 ぼくは,その後,先生の話を聞いて,何もかもやってもらうというのはやめて,自分からやってあげようという気にならないといけないと思った。 |
|||
| 戻る | |||
| 第78号(893) | |||
| 2002年2月13日(水)発行 | 「車いす一日体験学習」に取り組んで~その1~ この体験学習を出発点に,「バリアフリー」について考えていこう! |
||
| 先週から,子どもたちは,車いすの一日体験学習に取り組んでいます。一日一人ずつ,朝,学校に着いたらそのまま車いすを使って一日を過ごすのです。 昨年度の六年生にも取り組ませましたので,それを見ていた子どもたちはやる気満々でした。 ※ 階段の上り下りや,段差のあるところなど,必然的に友だちの介助が必要になるわけですが,自分たちの身の回りには車いすを使う人にとっての物理的な「障害」が,たくさんあるということに気づき,「私たちはどうすればいいのか」ということを考えるきっかけをつかんでくれています。 あと二日で,全員の体験学習が終わります。この後は,「とびうお」の時間に引き継いで学習を進めていきたいと思います。 ■子どもたちの感想・その一 車いす体験をして YD 今日,ぼくは一日中車いす体験をして,最初はとっても楽しみだったけど,だんだんはずかしくなってきました。それと少しの段差があれば,貴大君や卓朗君に助けてもらいました。だんだんやっいるうちにすごくめいわくをかけているなあと思いました。授業などが始まる前に階段からおりるとき,ぼくが一人じゃおりれないから,みんな手伝ってくれました。すると,なぜか,かってにありがとうと言葉がでました。昼休みも,みんなは遊んでいるけど,ぼくは車いすに乗って,見ているだけだったので,足が悪い人の気持ちが分かるような気がしました。 きょうは,たくさんのバリアフリーがあるけれども,もっともっとふやしていって,車いすに乗っている人がもっと便利なようにしてほしいです。この車いす一日体験をしてたくさんのことが分かりました。 車いす体験レポート HT 今日は,ぼくが車いす体験の日。ぼくは,車いす体験で階段は,自分でおりられないし,あがれないし,大きい物を持ったりできないので, 不便でした。だけど,不自由な人にはいい移動手段だけど,してもらうばかりで自分は,何もできないので,自分がダメに思えてきて,障害者の人達も体調的にも気持ち的にもつらいんだろうなあと思った。 ■今年もやりました,ミクロの生きもの探し。 び生物さがし US 二月一日,落ち葉拾いがあった。ピピーッという終わりの笛が鳴った。下に集まると中で,五時間目に土の中のび生物探しをするための土をとって,下に集まって帰った。そして,五時間目,四グループに分かれて,けんびきょうを一グループに二台ずつで調べた。 なかなか見つからない。すると, 「見つけたー。」 大地君が言った。みんなおどろいた。 その後,江里奈さんも見つけた。見つけた人には,そのび生物をかいてもらった。 今回はぼくは見つけられなかったけど,今度は見つけたいです。 び生物さがし YD 今日,五時間目にび生物さがしをしました。神社で土を取って,けんびきょうで見て何回か見ていると,少し動く物があったので,よく見てみると,び生物でした。 び生物は,ぼくたちの足の下でも,一〇〇〇びきはいるんだなあと思いました。ぼくたちの見つけたび生物は,へんな長いのでした。もっとたくさんび生物さがしたいです。 び生物をさがして OT 五時間目にび生物を探しました。グループに分かれ,とってきた土をけんび鏡で見ました。最初,光があたらず,ドアの方に移動しました。すると,土がすごくきれいに見えました。 大地君が最初に見つけました。でも,ぼくは見ませんでした。結局見つからず,見ればよかったなあと思いました。でも,び生物はいて,地下でちゃんと動いているんだと改めて分かりました。 び生物を探して HS 今日,五時間目に,五年生といっしょに落ち葉こひろいのときにひろった土の中に,微生物がいないか探した。四つの班に分かれて探した。私は,愛理さんと一緒にした。私達は,一匹も微生物を見つけられなかったけれど,大地君たちが見つけた微生物を見せてもらった。とうめいっぽくて,細かった。江里奈さんのは,細長くて足がたくさんあった気がした。あっというまに一時間が終わってしまった。とても楽しかった(けど,目が疲れた)。 微生物 HT 落ち葉拾いで持ってきた土の中に微生物がいるか調べた。みんなで土を調べ竹度,すぐには見つけられなかった。 ぼくがのぞいたけんびきょうには,ダニがいたけれど,けんびきょうが動いてしまってどこかへ消えてしまった。だけど,微生物が土を作り,植物を育て,植物は酸素を出してぼくたち(動物)が生きていることが分かった。 |
|||
| 戻る | |||
| 第79号(894) | |||
| 2002年2月15日(金)発行 | 「車いす一日体験学習」に取り組んで~その2~ 足が不自由な人にはいい移動手段となる車いすも,周りがそれに 合っていないとせっかくのいい移動手段も大変になるんだ…卓 |
||
| 車いす一日体験学習,感想文(その2)をご紹介します。昨日,八名全員が終了しました。子どもたちは,いくつかの大事な課題を発見してくれたようです。 車いす体験をして HS ついに,車いす体験の日がやってきた。私は,ドキドキしていたけど,一つだけ心配していることがあった。それは,体重。階段を運ぶとき,持ち上がらなかったらどうしようと本気で気にして,毎日ふっきんなどをがんばったけど,むだだった。 朝,学校へ着くと,みんなが来るまでまたなければならなかった。朝は,女子に運んでもらった。三人しかいないのに,がんばってくれて,すごくうれしかった。朝は,読書タイムや仲良し国語などがあって,小さい移動にいつもの倍以上の時間がかかり,とても不便だった。 パソコン室へ行くときなどは,男子も手伝ってくれた。階段では,すごくこわかったけど,本当に障害がある方は,私よりももっとこわいんじゃないかなと思った。 今回,この車いすの体験をしてみて,六年生の友だち(他の学年の友だちも),何も言わなくても,テストの提出をしてくれたり,本をとってくれたり,一人じゃできないことを手助けしてくれたりしてくれて,とてもうれしかった。それに,人にいろんなことをたのむときに,どんなに気をつかうか分かった。この学んだことを生かして,これから先,障害のある方を見かけたときは, 「何かすることはありませんか?」 と,進んで聞いて,進んで行動できるような人になりたい。 今日は,貴重な体験ができて本当によかった。 車いす体験をして KY 今日,初めての車いす体験だった。私は,体重は少しは気になっていたが,私が落ちないか心配だった。でも,補助者の方は,乗っている人を落とさないか,心配だと思う。朝,学校に来ると,静香さんがいた。男子は,まだ来ていなくて,困っていた。みんなは,まず学校に来ると,自分の足で六年教室までまで歩いて,ランドセルをおいて,また一階へ下りてきた。そして,六年生に持ってもらっていた。だから,私もそうすることにした。ランドセルをおき,一階へ下りてきた。その入れ違いで,男子と静香さんと早紀さんに協力して持ってもらった。でも,最初,早紀さんと静香さんが二人でもっていてくれた。三段目ぐらいから,男子が手伝ってくれた。今日は,仲良し体育。体育館に行くまで,静香さんがおしてくれたり,付き添いでいてくれた。何だか,付き添いや誰かが一緒にいてくれたりするとうれしい気分になった。階段。早紀さんと静香さんが二人だった。二人じゃバランスがなかなかとれなだろうなと思った。高橋先生が,最初手伝ってくださった。途中から,大地君が,来てくれて助かった。帰りには,静香さんと早紀さんだけでなく,男子も進んできてくれた。またもや階段。みんなで力を合わせて頑張ってくれた。机のところにすわると,いすでは自由に位置などが決められるけど,車いすでは,不自由だった。算数ではグループ。静香さんには,机を並べてもらった。卓朗君は,車いすをおしてくれた。三階でパソコン。また運んでもらわなければ…。みんなで進んできてくれてうれしかった。次は,社会。テスト配りも,車いすで行かねばならない。五年生も気をつかってくれて,机などをよけてくれてありがたかった。何も言わないでも,私のとりたいものをとってくれた。私は,これからも,今の生活がいいなと思った。普通に歩いているのがいいと思った。車いすでの生活は,大変だと実感。私は,この学習をして,人のありがたさ,不便さなどがわかった。これからどのようなことがあるか分からないけど,人にやさしく進んで行動ができるといいです。 車いす体験をして OT 今日,車いす体験をした。 朝,階段をのぼるのは,すぐみんな来てくれた。でも,何だか悪い感じがした。ぼくは,重いのでみんな大変だろうと思った。 車いすは,不便だった。ふつうに歩いている人よりもおそいし,教室も後のドアから入らないとだし,机にもまっすぐ入らないと何回も入れ直さないといけない。ななめに入ると,何か変な感じがしていやになる。それに,教室内の移動もつくえを動かしてもらったり,ろうかから入ったりしないといけない。それでも,やはり,階段の移動が一番不便だ。エレベーターがあればいいと何度も思った。階段が不便だと一番思ったのは,六時間目だ。できた作品を職員室まで持っていくときに,持っていけない。しょうがないから,放課後,良君に持っていってもらった。 その他に,いやだったのが,みんなが車いすをおそうとすることだ。行きにくい時におしてもらえるのはありがたいけれど,遊び道具のようにおされるのは何だかいやになる。 足が不自由な人にはいい移動手段となる車いすも,周りがそれに合っていないとせっかくのいい移動手段も大変になるんだと分かった。 これから,どんどん世の中がバリアフリーになっていくといい。 |
|||
| 戻る | |||
| 第80号(895) | |||
| 2002年2月18日(月)発行 | 「車いす一日体験学習」に取り組んで~その3~ 障害者の人たちは,本当にはずかしいのか? 私たちと障害者は,本当に反対なのか? …みんなでぜひ考えてみたい。 |
||
| 車いす一日体験学習,感想文(その3)をご紹介します。これから考えてみるべき,大事な感想が出てきました。 ※※※ 車いす体験をして IS 私は,車いす体験をして,こわいなと思ったことがある。それは,階段で上ったり下りたりするするときだ。このときは,友だちを信頼するしかないのだが,図工室に行くとき,ほぼ九十度に近い角度で上ったのは,少しこわかった。 昨日まで,ほかの人の車いす体験を見ていたけど,ただごとじゃないなと思った。だから,毎日車いすの生活をしている人は,段差や階段を上がったり,下りたりするとき大変だと思う。 だけど,平らなところを行ったり来たりするのは,少し楽だった。でも,遠くまで行くのに手が痛くなったり,カーブするときがやっぱれ大変だった。車いすマラソンに出ている人はすごいと思った。 『五体不満足』の乙武さんは,電動車いすを使っている。車いすの生活の人のために,もっといい設備の工夫をしたらいいと思う。そのためには,まわりの人も気をつかわないといけないと思う。 この車いす体験で,バリアフリーについて,もっと考えないといけないことが分かった。 車いす体験をして US 今日は,ぼくのま車いす一日体験の日でした。ぼくは,車いすにのる前に,気になっていることがありました。それは,体重です。ぼくは,重いので,みんなもてるかなあと思いました。でも,みんながんばってくれました。とてもうれしかったです。 あと,移動するとき,みんなからじろじろ見られるのがはずかしかったです。 障害者の人たちは,はずかしいのかなあと思いました。 車いす体験をして TM 今日は,私が車いすの日。私は朝,車いすのことをすっかり忘れてしまっていた。そして,仲良し体育が終わってから車いすだった。 私は,階段をのぼる時,すごくいやだった。なぜなら,私は,最近,体重がふえたから。イヤでも上らなければならない。みんな,「軽い」と言っていたが,重かったらどうしようと思っていた。そういうことを考えている間に,階段は終わった。そして,教室まで行って中に入った。入るときも少し大変だ。後から入らないといけない。よーく考えて見ると,障害者の方は,すっごく大変なんだと思った。私は,何回も車いすなのに立ってしまった。やっぱり,ふつうの生活がいいなあと思う。 車いすの方は,どんな思いで車いすに乗っているのだろう。私たちにとって「車いす」は,けっこう不便な物。障害者の方には,便利でいい移動手段。私たちと障害者の方は,反対なんだなあと思った。 ■□ゴール目指して!(その2)□■ 卒業アルバム・卒業文集作成,順調に進んでいます! 昨日予定していました,ガードレールのペンキ塗りは,残念ながら実施することができませんでした。天気を恨んでいます。子どもたちを通して,日程を調整したいと思いますので,どうぞよろしくお願いいたします。 さて,子どもたちの卒業アルバムと卒業文集の作成は,順調に進んでいます。 アルバムの方は,現在,三分の二ができあがりました。月行事の関係で,できあがりは三月中旬になりますが,予想したよりスムーズに進んで,安心しているところです。子どもたちのレイアウトセンスもよく,なかなかいい仕上がりになっていますよ。 また,文集の方は,現在国語の時間に,卒業作文(小学校生活を振り返って,自分を成長させてくれたもの・ことについて書く)に取り組み,ほぼ書き上げられています。これから先は,それぞれ分担したアンケートや「歩み」など,具体的なページの編集が始まります。こちらの方は,四分の一が済んだ段階といえるでしょうか。保護者の皆様からの原稿も,よろしくお願いいたしますね。 もう一つ卒業関係では,卒業式の「呼びかけ」台本の案ができました。職員会議で先生方に検討してもらい,最終決定となります。六年生は,暗記しなければならない文の量がとても多いので,早めに練習に取り組んでいけたらと思います。 それにしても,子どもたちは大変! お家の皆様,応援よろしくお願いいたします。 |
|||
| 戻る | |||